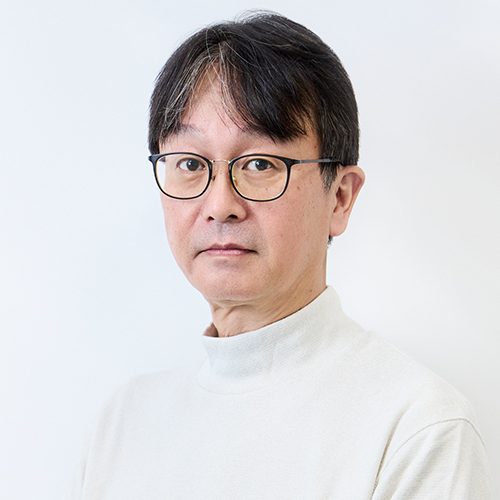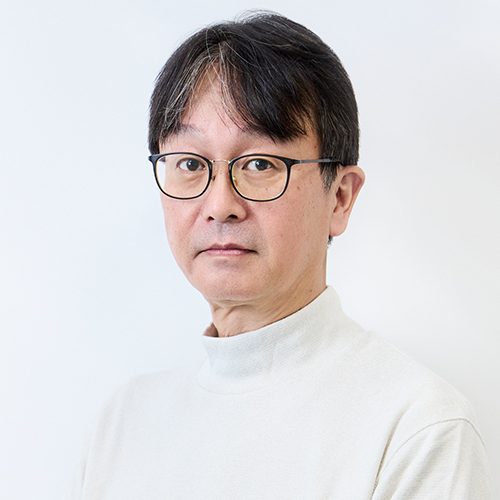
- 受賞作:
- 『ウェットランド』
- 受賞者:
- 服部 倫(はっとり りん)
- 受賞者略歴:
- 1969年2月3日、長崎県長崎市出身。大阪大学大学院博士後期課程修了。現在、大阪府豊中市に在住。介護職員。
- 選考委員:
- 月村了衛、中山七里、葉真中 顕、湊かなえ
- 選考経過:
- 応募191編から、2次にわたる選考を経て、最終候補4編に絞り受賞作を決定。
受賞の言葉
新人賞
服部 倫(はっとり りん)
小説を書いてみたい気持ちは昔からありました。応募も初めてではありません。
しかし、公募賞のたぐいを自分が受賞できると本気で思ったことはありませんでした。わりと単純に確率の問題として、受賞に足る作品を書ける可能性はかぎりなく低い。選考過程のどこかで落ちるのだろうなと思っていました。
本作は、「どうせ落ちるんだから、書きたいことをきちんと書いておこう」という姿勢で臨んだものです。私の感覚や好みをストレートに出しました。だから自分の中で納得できる作品にはなっています。
ただ、それは他者にそうそう受け入れられないだろうなと。こんな、いわば「ワガママ」な作品は、最終選考に残っただけで奇跡だと。本気でそう思っていました。
なのに本作は望外の評価をいただきました。ほんとうにありがたく思います。つたない作品を読んでくださった選考委員のみなさま、また関わってくださったみなさまに、心から感謝を申し上げます。
選考委員【選評】(50音順)

新人賞選考委員、左より葉真中顕氏、月村了衛氏、湊かなえ氏、中山七里氏。
月村了衛
「ウェットランド」は作品の空気感にも、語り手たる主人公をはじめとする人物達にも、大いに好感が持てる作品だった。大阪弁による軽妙な語り口だが、本質は極めて正統派のハードボイルドである。ゆえに本作の場合、ミステリ要素の弱さや真相が読めてしまうといった点はさほど気にならない。大事なのは主人公が自らの生き方を貫いていく小説であることだ。音楽の描写一つとっても作者の力量は明らかである。文句なく推した。
「幻影」は受賞作と並び強く推した。この心理劇に私はとても惹きつけられたが、他の委員の賛同を得られず、残念ながら同時受賞は叶わなかった。作者にはぜひ次回も挑戦して頂きたいと切に願う。
「リノベーション・デッドライン」作者の作品を私は過去にも読んでいるが、着実に上達しているものと評価する。しかし人物がストーリーの都合で動いているという点は否定できない。例えば不動産契約のシーンで、それなりに経験を積んでいるはずの主人公が不審に思いつつも契約してしまうあたりは相当に不自然だ。他にも無理のある状況や設定が目について、受賞レベルには至っていないと判断せざるを得なかった。
「銀眼の聖女」の作者に、書きたいものがあることは伝わってきた。しかし「犯人しか知り得ない情報」が警察によって秘匿されない、情景描写等が殆どないといった欠点が多く目についた。人物像もすべて定型通りである。以下は私の推測であり、違っていたら申し訳ない限りだが、作者の読書傾向はかなり狭い範囲に限られているのではないか。そのジャンル・様式を極めるという道もあるが、一般文芸の新人賞を目指すのであれば、より幅広く小説を読み、様々な文体や表現と出会うことが最善の道となる。そうすれば、自身の想いを一層深く効果的に伝えられるのではと愚考する。今後の奮起を期待するばかりである。
中山七里
選考会で大きく討議された評価軸は小説としての出来とミステリーとしての出来だった。しかし僕は売れるか否かを評価軸に加えた。売れ行きなど版元に任せればいいという意見は既に過去のものであり、今や選考段階で討議しなければならないほど切実な問題になっている。デビュー作が売れなければ荊の道どころか道そのものが途絶してしまうのだ。
受賞作の「ウェットランド」は最初の投票で最高点を獲得した。こなれた語りはリーダビリティを加速させ小説として完成度が高かった。何より主人公トリオのキャラクターがいい。舞台の大阪と相俟ってからりとした雰囲気を醸し、タイトルとは真逆の読み心地になっている。ミステリーとしての不充分さに関しては同賞の種目が広義のミステリーであることから許容範囲と判断した。各委員から指摘された瑕疵もストーリーの軽快さで相殺できる。受賞おめでとうございます。
対抗馬の「銀眼の聖女」はミステリーというジャンルの中でも更に狭小なカテゴリーで評価される作品だろう。二転三転する真相も読者を飽きさせない。お好きな人には堪らないだろう。しかし小説としての完成度を考慮すると、一般読者の食指を動かせる内容とはあまり思えない。少なくとも同賞の受賞作として推すには抵抗があった。捲土重来を祈る。
「幻影」も相応の時間を費やして討議されたが、僕には250枚で語れる内容を制限枚数である350枚に水増しした印象が強かった。小説にはサイズ感が不可欠であり、こればかりは作者のセンスに委ねるしかない。また、手記だけでそこまで他人を誘導できるかどうかにも疑問が残った。
「リノベーション・デッドライン」は申し訳ないが全てが足りなかった。最初から読む気を殺ぐ比喩表現が続き、作品世界になかなか没入できない。主人公のホテル再建に対する動機に共感性を持たせ、自らが捜査しなければならない必然性を強化してほしかった。
葉真中 顕
積極的に推したい作品はなかった。最終に残らなかった者も含め全応募者に「推敲してますか?」と訊きたい。答えがノーなら論外だし、イエスなら圧倒的に推敲不足だ。本賞は受賞すれば作品が出版される賞である。書店で平積みになっている人気作家の作品群と鎬を削ることになるのだ。自分の作品がそのレベルに達しているのか、厳しく客観的に見る目と、妥協なき推敲をやり切る胆力を養ってほしい。
「リノベーション・デッドライン」ホテルを開業するという話の軸は魅力的だが、文章力、キャラクター、個々のエピソード、ミステリとしての構造、すべてに難があった。使いこなせていない比喩や大仰な表現は読んでいてつらい。文章を飾り立てることよりも、シンプルに洗練させてゆくことをまずは心がけてほしい。
「銀眼の聖女」意欲的な作品だと思った。独特な世界観と結末のサプライズは評価したい。が、やろうとしていることに技術が追いついていない。思わせぶりなばかりの描写はむしろ作品世界に入り込みづらくしている。銀眼の聖女の「能力」も三つもあるわりに活かし切れているとは言い難い。特殊設定ミステリは今一番競争が厳しいジャンルだ。やるならもっと練り込んでほしい。
「幻影」個人的には一番高い点をつけた。人物造形の甘さ、テーマの練り込み不足、散見される不自然な展開、余韻よりも逃げの印象が強くなってしまっているオープンエンドなどなど、瑕疵は多い。だが伸びしろを感じた。心理ミステリとしての枠はしっかり出来ており推敲次第で「化ける」と思った。が、他の委員に、キャラクターがあまりに記号的との指摘を受け、それはまったくそのとおりで反論しきれなかった。
「ウェットランド」完成度は頭ひとつ抜けていた。キャラクターも文章もいい。著者は書ける人だ。ただ、メインとなる事件の弱さ、真相がほぼ台詞だけで説明される点など、気になった部分も多い。相対評価で受賞に同意したものの、書ける人だけに本作での受賞でよかったのか一抹の不安もある。今後の活躍でこれが杞憂だったことを証明してほしい。
湊かなえ
「ウェットランド」ミステリー作品としては弱いけれど、ドラマーの主人公と聴覚障害を持つ少年の成長物語として、興味深く読み進めましたが、早い段階で少年は一時退場。聴覚障害である必然性はあったのだろうか。多様性を描きたいとしても、配慮が足りないのではないか。そんな不満が生じると、大阪特有のノリツッコミの会話の応酬も楽しむことができません。しかし、文章がうまく、登場人物も魅力的。修正を前提とした受賞に同意しました。おめでとうございます。
「銀眼の聖女」この作品に一番高い点数をつけました。特殊設定美少女探偵ものですが、序盤から終盤まで、謎解きを楽しむことができました。選考会では「日本ミステリー文学大賞新人賞」らしくないという声がありましたが、私はその定義付けは、この賞の将来性を狭めるものになるのではないかと危惧しています。こういうタイプの作品も受賞するのか、と読者だけでなく、来年度以降の応募者の門戸を広げる作品として強く推しましたが、設定の甘い部分、詰め込みすぎの箇所などに反論できず、力及ばず。会話については、物語のトーンが通底しているので、私はまったく気になりませんでした。応援していますので、がんばってください。
「リノベーション・デッドライン」終始、あまり好きになれない主人公の、ブログをまとめたものを読んでいる心地でした。頭に思い浮かんだ物語をそのまま書いていくのではなく、切り口や緩急の付け方など、構成を工夫することにより、同じ内容でも、もっと面白くなると思います。真相を二転、三転させようという熱意に好感を持つことができました。
「幻影」登場人物の内面の掘り下げは、匙加減を間違えると、過剰な自意識の垂れ流しとなります。視点を変えて同じ場面を描写する際は、新しい発見や気づきがなければ意味がありません。それらの調整ができれば、とても面白い作品を書ける方だと信じて、次回作をお待ちしています。
最終選考候補作
予選委員7氏=円堂都司昭、佳多山大地、杉江松恋、千街晶之、西上心太、細谷正充、吉田伸子+光文社文芸編集部が10点満点で採点、討議のうえ予選を通過し最終選考に残る作品を決定(候補者50音順)。
- 「幻影」
- 千酌ジョウ
- 「ウェットランド」
- 服部 倫
- 「銀眼の聖女」
- 三沢 洸
- 「リノベーション・デッドライン」
- 我 双又
応募総数191編から1次予選を通過した21作品は下記のとおりですが、その後1作品に失格要因があることが判明したため、最終的に20作品での選考となりました(応募到着順。同一応募者の作品はまとめました)。
- 「ヴィーナスの見知らぬ横顔」
- 野林賢太郎
- 「犬畜生の義」
- 伊藤水流
- 「未生の殺意」
- 松原 彗
- 「おそらく今は、虚像の」
- 谷門展法
- 「ウェットランド」
- 服部 倫
- 「レプンカムイの子弟たち」
- 雲井登一
- 「リノベーション・デッドライン」
- 我 双又
- 「業務代行依頼」
- 葛西京介
- 「モーツァルト殺人」
- 相羽廻緒
- 「幻のゴラッソ」
- 相羽廻緒
- 「未完の『*』を求めて」
- 相羽廻緒
- 「永遠の未完成」
- 山本純嗣
- 「夢幻の絡繰」
- 山本純嗣
- 「げんげ田を歩いていた」
- 駒井俊雄
- 「二つのR」
- 月寒暖陽
- 「キンドレッド・ラプソディ」
- 四方 響
- 「幻影」
- 千酌ジョウ
- 「銀眼の聖女」
- 三沢 洸
- 「盤上の迷宮」
- 中島礼心
- 「ラストランナー」
- N
- 「雛の棺」
- 高円寺くらむ
【予選委員からの候補作選考コメント】
円堂都司昭
たとえ書いている本人に悪気がなくても、結果的に差別的な内容になっていると思われる例が、しばしばみられます。国家、民族、性的指向、身体や精神の障がいなどに関し、昔の感覚のままで書いていると、更新された現在の価値観にふさわしくない表現になることがあるのです。作中での男女それぞれの位置づけや、関係のあり方についても、同様のことがいえるでしょう。
ミステリー小説は、犯罪をあつかうことが多いですから、それをなにかの属性を持つ人と安易に結びつけると、すぐに差別的な印象を与えてしまいます。トリックのネタや犯人の動機づけとして、無造作に属性を使うのもよくありません。価値観が昔のままの書き方だと、せっかく面白いはずのストーリーでも、古くさい小説のような読後感を与えて損です。この設定、このキャラクター、この表現は、今の時代の小説として正しいのか、受け入れられるのかと、自問する必要があるでしょう。
佳多山大地
予選委員の任も今年で7度目になります。今回ここで指摘するのは、当初から気になっていたことのひとつ。それは、ミステリーの登場人物を作者の〝ご都合〟で動かしている作品が少なくない、という問題点です。
小説の登場人物には、基本、常識的に動いてもらいたい。降りかかる困難や思いがけぬ誘惑をまえに、どのような行動を彼、彼女はとるのか? ことにミステリーの場合、作者の(それはたいてい作中の犯人の)都合のいいように被害者や目撃者が不自然に動きすぎてはいけない。常識的な人間にちがいない大多数の読者は、それにより作品世界に入り込めなくなってしまいます。
――ところで。まったく常識外れのおかしな人物は、おかしな人物なりの論理に従って、むしろ常人よりも論理的に行動する。と、これはミステリーの世界における一種の神話といえますが、サプライズの利き目となるそういう人物は1作品にせいぜい1人であるからこそ利き目となるのだと思います。
杉江松恋
応募作全般に言えることなのですが、着想を小説の形にしたことで満足してしまい、その先に進めなくなっている書き手が多いと感じました。小説の独自性が最後に明かされる真相部分にしかない。そうなると結末に早く辿り着こうとして一本調子になるか、途中の展開に困ったらキャラクターやイベントを増やして切り抜けるかのどちらかで、前者は骨と皮ばかり、後者は贅肉のつけ過ぎでいただけません。ミステリーの種明かしは魅力の一つにすぎず、どのような物語のうねりがあるか、それはどういう種類の素材で組み立てられるか、という、中途の展開が本当は読ませどころなのです。物語を支える柱を三本は準備し、それらがどう補完し合うかを考えながらストーリーを構想してみてはいかがでしょうか。
文章も必要条件だということも忘れずに。今回、文体を評価した作品には、それだけで少し加点しました。最後は音読してみるといいと思います。あなたの文章に魅力はありますか。
千街晶之
今回の応募作に目を通して感じたのは、「犯人の行動のひとつひとつにもっと必然性を持たせてほしい」ということだった。犯行計画にさほどメリットがあるわけでもないのに、わざわざ派手な行動に走る犯人が登場する作品が目立った。その行動によって読者を引き込む効果はあるが、冷静に考えてみると、「どうして犯人はそんなことをしなければならなかったのか」という必然性が弱いのだ。ただでさえ犯人というのはやらなければならないことが多い立場なので、無駄な労力は費やしたくない筈である。
もうひとつ、少数民族などの社会的マイノリティの扱い方に雑さが感じられる作品も目立ったことを言及しておく。これは読者によって感じ方はさまざまだとは思うのだが、とはいえ予選委員の大半が問題があると感じてしまうような扱い方の場合、やはり商品として通用しにくいのではないだろうか。
西上心太
1次予選を通過した20作品から、最終選考に上げる4作品に絞る2次選考会の過程で気づいたことを縷々述べさせていただきます。
7人の予選委員の投票で、高低に突出した数作を除けば、八割方の作品の得点はなだらかな線を描いていました。それぞれ見るべき長所があったといえるでしょう。しかし評価の低い作品ほど御都合主義が目立ったことも事実です。
さらに性的嗜好、精神疾患、あるいは民族問題など、デリケートな問題を安易に取り入れた結果、「無神経」と捉えられかねない作品も散見されました。いまの時代にそぐわない社会通念によって構築された物語は、どんなに面白かろうが、それだけで忌避感を抱かれてしまいます。たとえばセクハラめいた描写でも、それが登場人物の性格を描くためにあるのなら問題ありませんが、そこから作者の無自覚さが透けて見えてしまう場合も多々あります。地の文における呼称でも、ついつい男性はファミリーネームで、女性をファーストネームで記しがちではないでしょうか。
あらゆる社会通念に敏感であり、自身が持つ「常識」を常にアップデートすることを忘れてはならないでしょう。選考する側の自戒も込めてしたためておきたいと思います。
細谷正充
本賞の応募枚数は、400字詰め原稿用紙換算で、350枚から600枚です。しかし600枚近い作品が多いですね。それだけの分量が必要な内容ならいいのですが、ストーリーが中弛みになっている作品が幾つか見られました。枚数の多寡で評価が決まることはありません。自分が書いている物語の求める分量を把握してほしいものです。
その他、昔からよくあるトリックを、安直に使用した作品も幾つかありました。使うなとは言いません。でも、今の時代の読者が感心するような工夫が必要です。このトリックの組み合わせは見たことがない、こういう使い方は初めてのようだ。そう思わせてくれる作品は、評価が高くなります。
また物語の内容が、特定の民族や人々に対する誤解を生むような書き方は、絶対にやらないようにしてください。題材として扱うならば、真摯に向き合ってください。社会のさまざまな認識は、どんどん変わっています。そのことをきちんと理解してほしいのです。
吉田伸子
今回、最初の得点で1位だった作品はすんなり最終候補に決まったのですが、残り3作をどの作品にするのか、予選委員の間で長時間の話し合いとなりました。今回は(最終候補にあげるのは)途中、3作でもやむなし、という意見も出ましたが、なんとか4作候補にあげることができてよかったです。
今回の2次選考で目についたのが、他の新人賞に応募した作品を「改稿」した作品です。以前の選評でも書きましたが、「改稿」というのはなかなかの大手術です。たとえば、犯人を変える、犯人の動機を変える、トリックを変える、くらいのものでなければ、「改稿」にはならないと思っていたほうが良いかと思います。そして、それほどの大手術をするのなら、新たに新作を、と思うのです。改稿してまで再応募するほどの思い入れがある作品かもしれませんし、気持ちを切り替えて新作に取り組むことは簡単なことではないかもしれませんが、大事なことではないでしょうか。